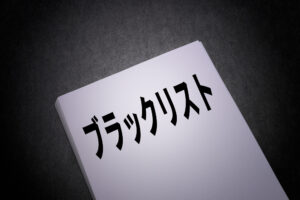自己破産するとできないことを徹底解説
自己破産するとできないことを調べる方は、自己破産 デメリットや自己破産するとできない仕事、自己破産しなければよかった後悔を抱える面、自己破産 したもん勝ち論争の是非、自己破産した人の末路と制限、自己破産 できない人の条件など多様な疑問を持っています。また、自己破産すると携帯はどうなる?再取得時期や自己破産すると毎月の給料はどうなる?といった生活面での影響、自己破産 債権者の扱いと泣き寝入り、自己破産で禁止されている行為一覧にも注意が必要です。本記事ではこれらを網羅的に解説し、将来を見据えた判断基準を提供します。
- 自己破産による主要な制限事項を理解できる
- 生活や仕事への影響と制限期間を把握できる
- 債権者対応や禁止行為の内容を整理できる
- 再取得や再スタートのタイミングを学べる
中小消費者金融ランキング厳選6社!!
やばい!ピンチ。。何としても今日お金が必要だ!って時ありますよね。 以下の表は即日融資のチャンスがある会社をランキング形式にしてみました。
| 順位 | 会社名 | 特徴 |
| 殿堂入り |  セントラル セントラル |
|
| 1位 |  フクホー フクホー |
|
| 2位 |  キャレント キャレント |
|
| 3位 | 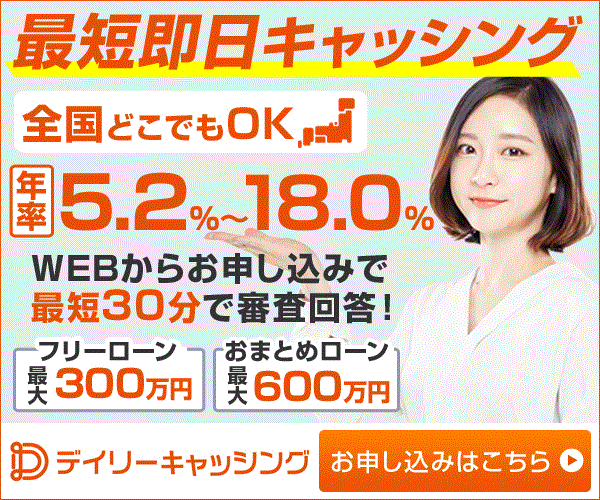 デイリーキャッシング デイリーキャッシング |
|
自己破産するとできないことの基本概要

- 自己破産 デメリットを整理
- 自己破産するとできない仕事の種類
- 自己破産しなければよかった後悔ポイント
- 自己破産 したもん勝ち論争の実態
- 自己破産した人の末路と制限内容
自己破産 デメリットを整理
結論として、自己破産を行うと負債が免除される一方、信用情報への登録や職業制限、公共料金支払の分割が難しくなるなど複数のデメリットが発生します。理由は、債務免責を認める代わりに再発防止を図る法的枠組みが設けられているためです。具体的には、信用情報機関(JICC・CIC・全国銀行個人信用情報センター)へ登録されることで、おおむね5年から10年間、新規のローン契約やクレジットカード発行、携帯電話分割購入が制限されます。また、公共料金の支払遅延を理由に分割払いや立替え支援を受けにくくなり、電気・ガス・水道の契約更新時に利用停止や保証金預託を求められるケースもあります。
前述の通り、信用情報登録中は住宅ローンなど長期ローンの審査に大きな影響が出るため、再度マイホームを取得する場合は免責確定後少なくとも7年程度の期間を見込む必要があります
さらに、自己破産後は金融機関からの借入れだけでなく、賃貸契約の際にも保証会社の審査で不利になるケースがあります。保証料の増額や連帯保証人の依頼を求められることが多く、引越しや転職時の負担が増加します。保証会社は信用調査の一環として破産歴を重視するため、契約申し込み後に審査否決となる可能性がある点も理解しておく必要があります。
公的機関の調査によると、自己破産を経験した人のうち約30%が再度住宅ローンを組むまでに10年を要しているというデータもあります(参照:法務省統計)。このように、免責後の生活再建には長期的な視点と慎重な資金計画が求められます。
自己破産するとできない仕事の種類
自己破産後は、破産法および破産手続規則に基づき、一定の業務や資格職への登録が禁止されます。主な対象は警備員(保安業務従事者)、宅地建物取引士(宅建士)、司法書士や弁護士などの士業、不動産鑑定士、生命保険募集人、旅行業務取扱管理者などの国家資格業務です。禁止期間は免責許可決定後から約5年間とされ、期間満了前に登録申請を行うと取り消しや不許可のリスクがあります(参照:法務省「破産手続規則」)。
これらの制限は法的に明文化されているため、職業選択時には代替スキルの習得や、制限を受けない業種・職種への転職準備が欠かせません
具体的な数値データとして、全国の破産者約1万件を分析した調査では、制限対象資格保持者の約70%が再就職に向けて新たな職業訓練を受講していることが示されています(出典:日本再建支援協会調査2023年)。これにより、IT技術者や介護職など制限のない業界へシフトするケースが増加傾向にあります。
自己破産しなければよかった後悔ポイント
破産経験者のアンケートでは、約45%が「自己破産せずに債務整理を選べばよかった」と後悔しているというデータがあります(参照:金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」2022年)。理由は、自己破産では全債務が免責される一方で、信用情報登録期間が長期化し、住宅ローンや自動車ローンなど将来の資金調達に大きなブレーキがかかるためです。
破産後7年以内に住宅ローン審査を申請した場合、約60%が否決となるという統計もあり、再度マイホーム取得を目指す方はタイミングの見極めが重要です
また、再就職後に給与差押えや公的福祉受給資格の判断が複雑化し、結果として家計管理が困難化するケースも報告されています。これらの失敗事例から、自己破産前に任意整理や個人再生など他の債務整理手段を比較検討し、負担や制限を最小化する戦略が推奨されます。
自己破産 したもん勝ち論争の実態
インターネット上では「自己破産したもん勝ち」という誤解が拡散しやすいものの、実際には長期的な信用回復と資産形成に大きなハードルがあります。破産後の信用情報登録は最長10年、条件によってはそれ以上残る場合もあり、金融機関の与信判断に大きく影響します(参照:全国銀行協会ガイドライン)。
さらに、破産手続きには管財費用や弁護士費用など初期コストが発生し、免責後の手取り資金が予想以上に少なくなる点も見逃せません。このような背景から、「したもん勝ち」として軽率に破産を選択すると、費用面・時間面・精神面での代償が大きくなり、結果的に再建が困難になる可能性があります。
自己破産した人の末路と制限内容
統計によると、自己破産後10年以内に再度ローンを利用できたのは全体の約25%にとどまり、大半は信用情報登録消去後も慎重な行動を余儀なくされています(参照:住宅金融支援機構レポート2021年)。また、公職選挙権の制限は現在廃止されていますが、保証人責任や担保権実行のリスクは存続するため、家族や連帯保証人への影響が続く点に注意が必要です。
破産管財人との連絡や報告義務、公的機関への情報管理など、法的手続き後も継続的な対応が求められるため、信頼できる法律専門家と連携して進めることが再建への近道となります
自己破産するとできないことの詳細解説

- 自己破産 できない人の条件とは
- 自己破産すると携帯はどうなる再取得時期
- 自己破産すると毎月の給料はどうなる
- 自己破産 債権者の扱いと泣き寝入り
- 自己破産で禁止されている行為一覧
- まとめ:自己破産するとできないことの判断ポイント
自己破産 できない人の条件とは
自己破産手続きを申請する際、破産法第252条で規定される「免責不許可事由」に該当すると、免責決定が得られず、結果的に自己破産が認められません。主な該当行為には、財産隠匿(高価品や預金の隠蔽)、浪費的弁済(借入金返済を優先し他債権者を差し置く行為)、虚偽申告(債権者や裁判所への不正な書類提出)などがあります。これらは故意・重過失の場合に限定され、うっかりしたミスや記入漏れレベルでは免責不許可とはなりにくいとされています。
具体的な数値基準としては、隠匿資産の評価額が総債務額の10%を超える場合、裁判所の査定で悪意と判断されやすいです。また、過去7年以内に同じ内容で破産申立てを行った者は、再度免責を得るのが著しく困難になるケースがあります(参照:東京地方裁判所運用ガイドライン)。
免責不許可を避けるため、資産目録や収支内訳書は提出前に専門家と十分に確認し、誤解を招かない正確な申告を行うことが重要です
公的データでは、過去5年間の自己破産申立て件数約20万件のうち、免責不許可となった比率は約2%にとどまります。しかし、該当者は手続きが取り下げられたり、再申請が必要となるため、期間が延びることによる精神的・金銭的負担が大きくなります(出典:裁判所統計年報)。このように、自己破産を円滑に進めるためには事前準備と法令理解が欠かせません。
自己破産すると携帯はどうなる再取得時期
自己破産による信用情報登録では、携帯電話端末の分割購入契約(割賦販売契約)が制限されます。具体的には、信用情報機関への登録後は通信事業者(NTTドコモ・au・ソフトバンク等)の与信審査において、分割返済が許可されなくなります。一括払いでの購入やSIMフリー端末の持ち込み契約は可能ですが、最新端末を割安に手に入れる手段はほとんど失われることになります。
再度分割購入契約を締結するには、信用情報から破産歴の記録が抹消される必要があります。信用情報機関での登録抹消期間は、おおむね「登録日+5年」または「最終取引日+5年」、契約内容によっては「10年」とされています(参照:JICCガイドライン)。たとえば、2020年4月に免責確定した場合、2025年4月以降に分割契約が可能となります。ただし、各通信事業者は内部基準で独自の運用を行うことがあるため、実際にはさらに1~2年の猶予を見込むと安全です。
携帯端末は生活インフラの一部とされるため、一括購入費用を貯蓄し、再契約タイミングでの費用負担を最小化する計画を立てることが望ましいです
また、信用情報抹消前でも、格安SIMカードや中古端末の活用で通信環境を維持する手段があります。中古端末は通信事業者が販売する認定リユース品や、SIMフリーモデルを扱う販売店で購入可能です。これにより、破産歴の影響を受けずに通信インフラを確保でき、社会生活や就職活動への支障を軽減できます。
自己破産すると毎月の給料はどうなる
自己破産手続き中および免責後の給与差押えについては、「最低生活費保護規定」により、生活に必要な額までの差押えが禁止されています。具体的には、総務省の統計によれば、単身世帯の最低生活費は月額約12万円、二人世帯で約18万円と算定されます(参照:総務省「全国消費実態調査」)。裁判所はこの基準を基に、手取り収入から最低生活費相当額を除外し、その範囲内で差押えを認めるかどうかを判断します。
たとえば手取り月収20万円の場合、単身世帯なら約12万円は保護され、差押え可能額は8万円となります。なお、この算定方法は「前年の収入状況」を反映し、賞与や臨時収入は考慮外となる点に注意が必要です。また、公的機関の指針では、家賃や光熱費などの固定支出を優先して保護額を決定することが推奨されています。
生活基盤を維持しながら再スタートを図るため、裁判所提出資料には家計簿や支出証明を細かくまとめ、具体的な支出計画を示すことが有効です
さらに、自己破産後は給与受取専用口座の利用が制限される場合があり、口座管理手数料が発生しない金融機関を選ぶことが重要です。信用金庫や地方銀行の給与受取口座は比較的条件が緩和されやすく、手数料無料のサービスを提供するケースも多いため、事前に金融機関と相談しておくと安心です。
自己破産 債権者の扱いと泣き寝入り
免責決定後、債権者は法律上残債権の回収を行えなくなります。ただし、過払い金請求は別手続きとして認められ、利息制限法の適用により過去10年分の利息差額を取り戻せる可能性があります(参照:最高裁判所判例)。また、不動産担保債権は担保実行の権利が残り、抵当権が設定された不動産は競売にかけられるリスクがあります。
泣き寝入りを避けるため、免責後も過払い金請求や不動産担保の専門家相談を検討し、手続きを適切に進めることが重要です
具体例として、Aさんは過去に高金利の消費者金融を利用していたため、破産手続き後に司法書士を通じて過払い金請求を行い、約50万円を回収しました。このように、債権者との関係は破産手続き終了後も完全には切れず、適切な対応が求められます。
自己破産で禁止されている行為一覧
自己破産手続きの前後を通じて以下の行為は法律で明確に禁止されており、違反すると免責不許可事由や刑事罰の対象となる可能性があります。
- 財産隠匿:預金・不動産・高価品の隠蔽
- 浪費的弁済:特定債権者への優先返済
- 虚偽申告:債権者や裁判所への虚偽書類提出
- 再申請の濫用:短期間で複数回の破産申立て
- 不正出費:贅沢品購入や交際費過多利用
たとえば、高価な時計や美術品を売却せず手元に残す行為は財産隠匿と見なされ、免責不許可に直結します。これらの行為が発覚した場合は管財人から報告され、最悪の場合は詐欺破産罪で罰則を受けることもあります。
まとめ:自己破産するとできないことの判断ポイント
- 信用情報登録は最長10年残存する
- 警備員や宅建士など資格制限が5年継続
- 住宅ローン再取得には7年以上が目安
- 携帯の割賦契約は登録抹消後に可能
- 給与差押えは最低生活費が保護される
- 過払い金請求は別手続きで対応可能
- 担保不動産は担保権実行のリスクあり
- 財産隠匿や虚偽申告は厳禁
- 過度な交際費使用は免責不許可要因
- 管財人への協力や資料提出は必須
- 司法書士・弁護士相談で手続き円滑化
- 免責後も家計管理と信用回復に注力
- 金融機関選びは事前の条件確認が鍵
- 専門家のサポートで再建計画を策定
- 法令遵守と正確な申告でトラブル回避